「資格なんて無くても実務はこなせるから不要では?」
「事務では必要だけど現場に資格は必要?」
など、工場の資格に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
工場で働く際には、扱う製品や業務内容ごとにマッチする資格を取得することで、昇給やキャリアアップに役立てることが可能です。
この記事では製造現場で働く工場勤務者にオススメの資格について、
理由、合格率、受験資格を含めて解説しています。
自身のキャリアップや給料アップの参考にしてください。
以下、本ブログでは工場で働く人・働く事に興味を持っている人たちへ向けて下記を発信しています。
本ブログでは以下の点が役に立ちます。
具体的な仕事のイメージが掴める
(自分が工場勤務に向いているか判断するのに役立ちます)
職場のリアルな声が聞ける
(求人情報だけでは分からない職場の雰囲気や大変な点なども知ることができます)
安定生活のためのノウハウ
(工場勤務というライフスタイルに合わせた収支管理、休日の過ごし方、健康管理の実践的なアドバイス)
知っておくと有利な予備知識
(事前に知っておくことでスムーズに働き始められる情報)
それでは解説していきます。
資格の目的
先ず、そもそも資格とは何を目的として存在するのでしょう?
関連する文献は見当たらなかったのですが、Wikipediaには下記が記されています。
日本における公的資格制度は、
「国民の権利と安全や衛生の確保、取引の適正化、資格者のモラル向上等のため、厳格な法的規律に服する資格者が存在し安心できるサービスを国民に提供すること」を目的として、
「国民の権利と安全や衛生の確保、取引の適正化等のために設けられてきた」
とされる[5]。
しかし、学校教育と深く関連付けられていたり、国家の統一的な基準により整備されていたりするわけでもないため、対象領域・種類や等級・取得ルートの各側面において極めて多様性の高い様相を呈しており、その役割を説明することは容易ではない[6]。
参考:出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_資格
・・・理解が難しいです。
要約すると
資格は個人の能力開発やキャリア形成を助けるだけでなく、
企業が適切な人材を確保し、社会全体が安全かつ円滑に機能する重要な役割を果たしている。
という所でしょうか。
Onobuさん
端的に言ってしまえば「業務が関連していれば、持ってて損は無いよね」って理解で良いと思います。
資格の種類
資格には大きく分けて3種類あります。
- 国家資格
国の法律に基づいて個人の能力やその業務に従事できることを証明する資格 「例:気象予報士」 - 公的資格
公的な背景がありながら国家資格ではない資格 「例:簿記」 - 民間資格
民間企業や団体が独自の基準で主催している資格 「例:英検」
資格取得のメリット
工場勤務者が資格を取得することには、以下のようなメリットがあります。
- 担当できる業務の幅が広がる
特定の作業や設備操作が可能になり、より多くの業務に携われるようになります。
- 専門知識・技能が身につく
業務に必要な知識や技術を体系的に学ぶことができ、仕事の質が向上します。
- 安全意識の向上
特に安全に関わる資格は、危険予知能力や事故防止の知識が高まります。
- キャリアアップに繋がる
資格手当が支給されたり、昇進・昇格の際に有利になったりすることがあります。
- 転職に有利になる
専門性やスキルを客観的に証明できるため、転職活動において有利になります。
工場勤務者へオススメの資格12選「製造現場編」
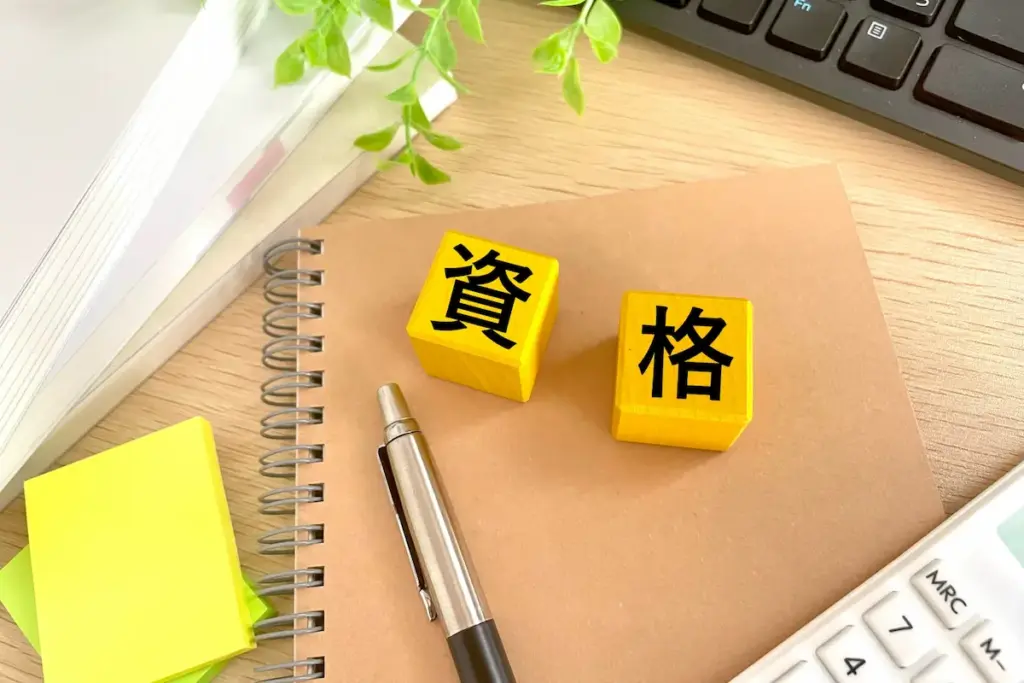
製造現場でオススメの資格を紹介していきます。
公式サイトにはリンクが貼ってあるので、興味を持った方はそちらから詳細及び応募が可能です。
フォークリフト運転技能講習/特別教育
オススメ理由 訓練給付金対象
フォークリフト運転技能者は、
工場内や倉庫内に運搬荷下ろしをする際に必要不可欠な、非常に需要の高い資格です。
フォークリフトは、どんな工場でも必ずと言っていい程使われているので、
この資格を持っているだけで工場内運搬部署では即戦力間違いなしです。
| 資格分類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 18歳以上 |
| 合格率 | 90%以上 |
| 公式サイト | 自動車教習所 |
玉掛け技能講習
オススメ理由 訓練給付金対象
工場や建設現場で資材や荷物をクレーンで持ち上げる際に、
クレーンフックに荷物を引っかけたり、外したりする事ができる資格です。
大きな製品や重量物を取り使う工場では、必ず使われます。
取得して最初の頃は、自分の引っかけた荷物が落下しないか緊張してたのを覚えてます。
| 資格分類 | 国家資格 ・1t未満 ・1t以上 |
| 受験資格 | 18歳以上 |
| 合格率 | ・1t以上、未満:90%以上 |
| 公式サイト | 一般社団法人 日本クレーン協会 |
ガス溶接技能講習/アーク溶接等特別教育
オススメ理由
金属の溶接や溶断に必要な資格です。
これらの技術は製造業の多くの現場で用いられており、資格があることで担当できる作業が広がります。
見た目キレイに溶接できても、曲げ試験とかで折れると自分の技能の未熟を痛感します。
取得は容易ですが、技能は奥が深いですね。
| 資格分類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 18歳以上 |
| 合格率 | 「アーク溶接等の業務に係る特別教育」を受講:ほぼ100% |
| 公式サイト | 商工会議所や一般企業、公的機関 |
有機溶剤作業主任者技能講習
オススメ理由
有機溶剤を扱う作業場で、作業方法の決定や指揮、保護具の使用状況の監視などを行い、
作業者の健康障害を予防するための資格です。
化学工場や電子部品工場などで特に重要視されます。
| 資格分類 | 国家資格 |
| 受験資格 | なし |
| 合格率 | 90~95% |
| 公式サイト | 一般社団法人労働技能協会 ※上記は東京を載せてます。 |
小型移動式クレーン運転技能講習
オススメ理由 訓練給付金対象
吊り上げ荷重5トン未満の移動式クレーンの運転に必要な資格です。
比較的規模の小さい現場での荷揚げ作業などで役立ちます。
「ホイストクレーン」と呼ばれたりしてます。
慣れない内は持ち上げた荷物を運搬する際に、荷物が左右に大きく揺れて危険なので、難しいんですよね・・・
滑らかに操作する人がカッコよく見えます。(笑)
| 資格分類 | 国家資格 |
| 受験資格 | なし |
| 合格率 | 95% |
| 公式サイト | 一般社団法人日本クレーン協会 |
危険物取扱者
オススメ理由
消防法で定められた危険物を、製造、貯蔵、取り扱い、運搬する際に必要な資格です。
特に乙種4類はガソリンや灯油など多くの工場で扱う機会のある危険物に対応しており需要が高いです。安全管理に関する知識が身につきます。
余談ですが、僕の娘が中学生で乙種1~6種全て取得して学校で表彰されてました。
素直に感心してます。
親は未取得なんですけどね・・・
| 資格分類 | 国家資格 ・甲種、乙種(1類~6類)、丙種 |
| 受験資格 | 甲種: ・大卒 ・乙種取得で実務2年以上 ・乙種指定4種類以上 上記3つのいづれかを満たしているもの 乙種、丙種:なし |
| 合格率 | 甲種:20~30% 乙種:30~40% 丙種:60~80% |
| 公式サイト | 一般財団法人 消防試験研究センター |
衛生管理者
オススメ理由
従業員50人以上の工場で必ず1名以上選任する必要がある資格です。
職場の労働環境の衛生的改善や、従業員の健康管理に関する業務を行います。
労働安全衛生に対する意識向上に繋がり、管理者へのステップアップにも有利です。
| 資格分類 | 国家資格 ・第一種衛生管理者 ・第二種衛生管理者 |
| 受験資格 | ・大学(短大を含む)または高等専門学校を卒業:1年以上の労働衛生の実務経験 ・高等学校または中等教育学校卒:3年以上の労働衛生の実務経験 ・学歴の条件に当てはまらない:10年以上の労働衛生の実務経験 |
| 合格率 | 一種:40~45% 二種:50~55% |
| 公式サイト | 安全衛生技術試験協会 |
電気工事士
オススメ理由 訓練給付金対象
工場内の電気設備の工事やメンテナンスに必要な資格です。
設備の安定稼働に貢献し、専門性の高い業務に携わることができます。
第一種と第二種があり、扱える電圧範囲が異なります。
| 資格分類 | 国家資格・第一種電気工事士 ・第二種電気工事士 |
| 受験資格 | なし |
| 合格率 | 1種:60~64% 2種:65~70% |
| 公式サイト | 一般財団法人 電気技術者試験センター |
ボイラー技士
オススメ理由
工場などで使用されるボイラーの取り扱いや安全管理に必要な資格です。
エネルギー供給に関わる重要な設備であり、安定稼働に貢献できます。
特級、一級、二級があります。
| 資格分類 | 国家資格・特級ボイラー技士 ・一級ボイラー技士 ・二級ボイラー技士 |
| 受験資格 | ・特級:一級ボイラー技能士免許を受けた物 ・一級:二級ボイラー技士免許を受けた者 ・二級:なし |
| 合格率 | ・特級:20~25% ・一級:40~45% ・二級:50% |
| 公式サイト | 安全衛生技術試験協会 |
機械保全技能士
オススメ理由
工場設備の点検、保守、修理に関する技能を証明する国家資格です。
設備の安定稼働や生産性維持に貢献し、機械トラブルに対応できる専門人材として評価されます。
等級があり、上位等級ほど高度な知識・技能が求められます。
| 資格分類 | 国家資格 特級、1級、2級、3級 |
| 受験資格 | 特級:実務5年以上、1級持ち 1級:実務7年以上、2級持ち実務2年以上、3級持ち実務4年以上 2級:3級取得者、実務2年以上 3級:なし |
| 合格率 | 特級:20% 1級:27.5% 2級:32.5% 3級:76.5% |
| 公式サイト | 公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 |
品質管理検定(QC検定)
オススメ理由
製品やサービスの品質管理に関する知識・能力を評価する民間資格です。
品質改善活動に貢献でき、製造業において品質保証は非常に重要なため、多くの企業で評価されます。
レベルが分かれており、段階的に学習できます。
| 資格分類 | 民間検定 ・1級 ・準1級 ・2級 ・3級 ・4級 |
| 受験資格 | なし |
| 合格率 | ・1級:10% ・準1級:19% ・2級:25% ・3級:55% ・4級:85% |
| 公式サイト | JSAGROUP 日本規格協会グループ |
CAD利用技術者試験
オススメ理由 訓練給付金対象
CADソフトを使って図面を作成・修正するスキルを証明する資格です。
設計部門や製造準備段階で役立ち、業務の効率化に貢献できます。
2次元と3次元があります。
| 資格分類 | 民間資格 3次元1級、準1級、2次元1級、2級 |
| 受験資格 | 3次元CAD1級/準1級:3次元2級持ち 3次元CAD2級:なし 2次元CAD1級:過去の2次元1級持ち、2次元CAD2級持ち 2次元CAD2級:なし |
| 合格率 | 3次元CAD1級/準1級:30% 3次元CAD2級:55% 2次元CAD1級:40~50% 2次元CAD2級:53% |
| 公式サイト | CAD利用技術者試験 |
資格を選ぶ際のポイント
- 現在の業務への直結度
日々のルーチンワークの効率化や精度向上に役立つか、
特定の作業を行う上で必要な知識や技能が得られるかを考えましょう。
学んだことがすぐに実践に活かせる資格は、モチベーション維持にも繋がりやすいです。- 担当したい、あるいは将来的に任される可能性のある業務との関連
在の業務だけでなく、今後挑戦したい、
あるいは会社から期待されている(打診されている)業務に必要な資格であれば、
取得によってキャリアアップや業務範囲拡大のチャンスを掴みやすくなります。- 会社の事業内容や部署の役割との整合性
会社が力を入れている分野や、所属部署が果たすべき役割を理解し、それに貢献できる資格を選びましょう。
会社の戦略と合致する資格は、評価されやすい傾向にあります。- 上司や同僚からの評価・推奨
実際に職場で働いている先輩や上司に相談してみるのが最も有効な方法の一つです。
どの資格が実務で役立つか、取得するメリットがあるかなど、リアルな意見を聞くことができます。- 会社の資格取得支援制度の有無
会社に資格取得に関する費用補助、特別休暇、合格報奨金などの支援制度があるか確認しましょう。
会社が支援している資格は、会社がその価値を認めており、取得を奨励している証拠でもあります。
支援があれば、経済的負担も軽減されます。- 公的支援の有無「教育訓練給付制度」
厚生労働省が推奨する対象資格の場合、資格の難易度で受講費用の一部が給付される公的支援制度です。
対象資格の申請や詳細は、ハローワークで確認できます。
ハローワークインターネットサービス- 法令遵守との関連性
工場では、業務内容によっては法令で定められた資格(必置資格など)が必要な場合があります。
担当業務や職場がそうした資格と関連しているか確認し、取得が必要であれば優先順位が高くなります。
これは会社にとっての法令遵守に直接貢献することになります。- 取得の難易度と現実的な学習計画
業務と両立しながら学習することになるため、
「資格の難易度」「合格までに必要な学習時間」「試験頻度」などを考慮し、現実的に取得可能かどうかを判断しましょう。
無理な計画は挫折の原因になります。
まとめ

この記事で分かったこと
- 工場勤務者におすすめの資格は「安全・保全・運搬・品質・設計」など多岐にわたる
- 資格取得は「手当」「昇格」「転職」に有利で、現場での信頼にもつながる
- 合格率や受験資格もさまざまで、未経験者でも挑戦しやすい資格も多い
- 会社によっては資格取得支援制度(費用補助・報奨金・特別休暇など)がある
資格選びのヒント
- 現場でよく使う設備や業務に関連する資格から選ぶ(例:フォークリフト、危険物取扱者)
- 将来的に目指したいポジションに必要な資格を逆算して選ぶ(例:衛生管理者、電気工事士)
- 合格率や勉強時間を確認し、無理なく取得できるものから始める
- 会社の支援制度や先輩の体験談も参考にする
次にやるべきこと
- 自分の業務に直結する資格を1つ選び、試験日や申込方法を調べてみる
- 関連記事で「年収アップ」や「部署構成」もチェック
工場勤務の給料・待遇は資格の有無によって変わってくる。
給与・専門知識及び技能、キャリア向上、転職に有利。
資格によっては一定の学歴や、実務経験などの受験資格が必要な場合もある。
難易度を確認し、通信教育や公的支援「教育訓練給付金制度」などを利用して取得を目指す。
ご自身の現在の業務内容や、将来的にどのような仕事に携わりたいかを考慮して、
取得する資格を選ぶことをおすすめします。
未経験から始める場合は、比較的取得しやすい技能講習などから挑戦してみるのも良いでしょう。
あなたの現場ではどうですか?
「この資格が役立った」「取得後に昇格できた」など、あなたの体験談もぜひコメント欄で教えてください!
さぁ 皆さんも工場で働きましょう!

